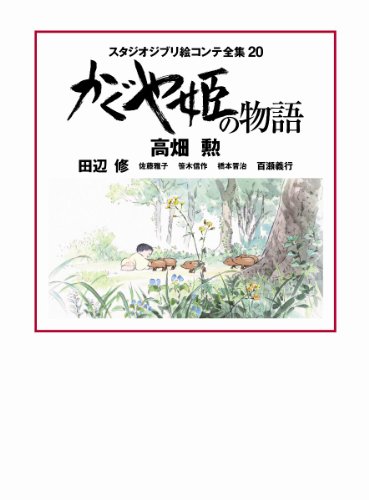『かぐや姫の物語』は、一言で言えば、「どこまでも味わい尽くしたくなる映画」だった(その3)
(その2)からの続きです。
まさに「生きたいように、生きている」日々を送っていたかぐや姫は、「誰もが憧れる都の暮らし」をさせてやろうという翁の願いによって都に出ることになる。
かぐや姫と翁と媼は都に出て大きな屋敷に住み、相模という家庭教師をつけ、斎部秋田という学者に「なよ竹のかぐや姫」という名前を付けてもらい(それまではタケノコのようにぐんぐん成長することから、「竹の子」と呼ばれていた)、髪上げの儀式が行われ、お披露目が行われる。ここのあれよあれよという展開の中で、かぐや姫の「自然」が奪われ、「文化・社会」の中に押し込められていく。それに抵抗しつつ、翁の願いを無礙にもできない。かぐや姫は都の屋敷の庭に田舎の風景を再現するなど、バランスを取りながら順応しようとしていくのだが、自分が御簾の中にいたまま開かれるお披露目の宴会の席で侮辱的な言葉を聞き、我慢しきれなくなってしまう。姫は屋敷を抜け出し、山の中に走っていくと、もと住んでいた田舎の家を訪ねるが、そこには見知らぬ人が住んでいて、知っている人はもう誰もいない。そして、ぼろぼろの姿で家の前に立った姫の前に施しが置かれ、住人は中に引っ込んでしまう。
ここがまた一つ印象に残るところだ。彼女は「施し」を拒まない。もらってよかったと思っているのか、その握り飯をほおばりながら道を降りていく。するとそこに炭焼きをする老人がいて、木地師たちは木を求めて場所を変えて行った(この辺、放浪民を描く網野史学が踏まえられていて、その意味で『もののけ姫』にも通じる世界がある)と姫に教える。
歩き疲れた雪の中で姫は倒れれるが、気がつくと元の京都の屋敷の御簾の中にいる。この雪げしきの描写と姫が着た衣装の純白が重なっているところは、絵で見せるアニメーションだからできることだなと思う。それは後に出てくる月の世界の真っ白な(色のない)清らかさと重なっていく。
行き倒れそうになる死に近い雪の世界=喜びも哀しみもない清浄な月の世界=都でかぐや姫が着せられた純白の衣裳。このイメージのメタファーの力が、生気に満ちた子どもの頃の風景や満開の桜の下で踊る姫のイメージに対比されて、もの悲しい。
この雪の中の炭焼きの声が実は仲代達也だ。この「大物がちょっとだけでる」という手法は芝居や映画では、「御馳走」と呼ばれるわけだけど、この映画ではほかに石作の皇子の北の方(まあ平安時代に北の方という呼称はないと思うが)の声を朝丘雪路がやっているというのもある。
朝丘はともかく、仲代もそうだけど、そのほかのキャラクターがみな声優をやった人たちの顔や姿かたちをどことなく思わせる風貌になっているのも、プレスコアリングというこの映画の特性が生かされていて面白いなと思った。
話はさらに脱線するが、私がこの映画で一番好きなキャラは(まあ主役のかぐや姫をのぞけばということだが)「女の童」(かぐや姫に仕える童女)なのだけど、この声をしている方はずいぶんきりっとした女優さんだ。この役はなんというか、いわゆる「おいしい役」で、まあ、私は芝居をしていた時によくこの種の役を演じていたので、なんだか思い入れを持ちやすいのかもしれないという気もする。ある種のトリックスターだから、構造がしっかりすればするほどその枠に収まりきれないで目立つことができて、印象に残る。そういう配役構造が、実は古典的に作られていて、観客に見えない安心感を与えているように思う。
(その4に続きます)