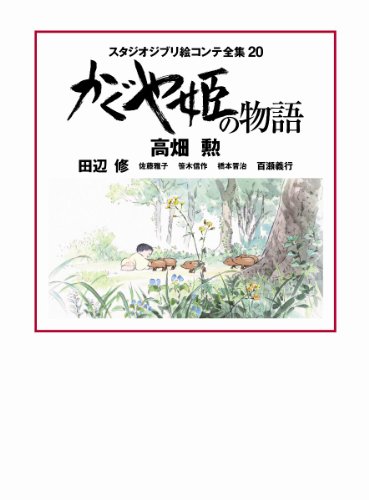『千と千尋の神隠し』再考:カオナシとは誰のことか――あなたの闇の葬り方
宮崎駿の映画には、初期には「悪役」が出て来るが、トトロ以後ははっきりとした悪役というのは出て来なくなる。だから悪役として明確に意識できるのはナウシカのクロトワとラピュタのムスカくらいなものだ。ジブリ映画で好きなキャラクターベスト10みたいな企画をどこかでやっていたが、女子はともかく男子対象でアンケートをとったらムスカがかなり上位に入っていて、これは明らかな悪者だからだろうと思う。男の子は悪者が好きなのだ。悪者というのは精神の異形者であって、異形の者への憧れというのがやはり男の子の中にはあるのだと思う。
それはそれとして、たとえば『もののけ姫』では明らかな悪者はいないわけではないけどみな小物だ。問題はそれよりも、暴走する自然をなだめ、すべての崩壊を食い止めること。タタリ神と化したイノシシや首を失って暴れるシシ神たち。しかし、自然が悪であるとか、人間に害をなすものという視点はない。自然は恐ろしいが、人間は自然の一部なのだから、その中で自然に対する畏れを知っていきるしかない、つまり人間には乗り越えられない何かがある、といえばいいか、それはつまり自然と対峙するときに自然と対決するとか自然を超克するとかいう姿勢を取ったときに人間としての破滅がはじまるということで、自然に銃口を向けることは結局自分自身に銃口を向けることになるのだ、ということではないかと思う。「悪」と対峙するのは話の作り方としては一定のルールがあるけれども、そうでないものと対峙する話の作り方の方が、より幅が広く、より難しく、より面白いように思う。
『千と千尋の神隠し』にも、明確に悪と言える存在は出て来ない。それじゃあ『千と千尋の神隠し』では何を言おうとしているんだろう、どういうふうに話が作られているんだろうと考えてみた。以下、この映画を見ていることを前提としての話になる。
まずテーゼを立ててみる。一言でいえば、それは、現代に生きるということは、たぶんある種の地獄というか、異界の中で生きるようなものだということかなと思う。その中で生きていても、精いっぱい自分がしなければならないことを生きることで、人は本来の自分を取り戻して行く。父や母や、愛する人たちのため、という思いもひとまずおいて、「自分のするべきことをしていく」ことで。ということではないか。
そう考えてみると、よくわからないけど物語の中心近くにいるカオナシという存在が千尋とコントラストをなすものとして浮かび上がってくる。「自分のするべきことをしている」千尋に対し、「自分のするべきことが見つからないで暴走する」のがカオナシなのではないかと。どこかで読んだのだが、『千と千尋』は構想しているうちにものすごく長大になってしまって、物語の中盤を創りなおしてカオナシを軸としたストーリーに変えたのだという。千尋が懸命に日々の仕事をつとめて行く一方で、カオナシはどんどん不安定さをあらわにし、異形なものになって行く。カオナシは偽物の金を出すことで湯屋のキャラクターたちをひきつけ、彼らを飲みこみ、そして彼らの欲望を自分の欲望として暴走し、何を食べても満たされない。貪欲とは欲望の満たされない状態なのだ。そして本当に求めている千尋には拒絶される。カオナシは絶望して暴走するが、しかしその千尋の拒絶と手助けによってカオナシは救われる。ニガヨモギの団子を食べさせられて他者の欲望を吐き出し、ハクを助けに行く千尋と一緒に電車に乗って銭婆のところに行き、そこに自分の生きる場所とすべきことを見つけるのである。
自分の生き方が見つからず、人の欲望を自分の欲望と勘違いして、自分では何もなさず、ただ人に求め、満たされない欲望を嘆く。作中にはそういう人間がほかにもいる。それは、この異界に迷い込む前の千尋自身だ。そう考えてみるとカオナシとは、あの世界に現れる前の千尋の姿なのだ、もちろん明示はされてないけれども。千尋が湯屋の世界に現れ、その存在が、両親を豚にされ、心細い状態でハクの手助けを受けて、それでも一大決心をして両親を救うために名前を奪われそうになりながらも決して忘れることなく(このあたりは『ルーツ』でクンタ・キンテが名を奪われ、トビーという奴隷としての名を押し付けられるくだりを思い出す)、自分の本当にやりたいこと=両親を救いだすこと、そして途中からはハクを救うこと=自分のすべきことをして、状況を乗りこえていく強い意志を持った千=千尋と、自分のすべきことが分からず、他人の欲望を飲みこんで自分の欲望と勘違いし、どんどん醜く太っていく(自我が肥大して行くのに空虚そのものである)カオナシの二つに分裂したと考えればよいのではないだろうか。
そして自分のすべきことを理解している千尋は、その空虚な自分を拒絶はするけれどもちゃんと手助けをして、そして彼を地獄や闇の中ではなく銭婆のメルヘンの世界に連れて行き、安住の地を与えて現実の世界に帰っていく。それが「大人になる」ということ、「大人になった」ということなのではないだろうか。
もちろん千尋だけでなく誰の中にも、空虚な欲望に振り回される自分というのはいるわけで、その空虚な自分にどう対すればいいのか、宮崎はその一つのヒントを示しているのだと考えてもいいのかもしれない。
これは『風の谷のナウシカ』漫画版において、「ナウシカは森の人に案内されて最も闇に近い存在として鋭く対立し続けた土鬼(トルク)の皇弟と一緒に清浄な世界に行くのだが、皇弟はそこで浄化されて帰って来ない」というくだりと、同じことが表現されているのではないだろうか。ナウシカは森の人に「闇から生まれた者は闇に帰すべきでした」と言われるが、ナウシカは「闇は私の中にもあります」という。「この森が私の内なる森なら、あの砂漠もまた私のもの。だとしたらこの者はすでに私の一部です」という。ナウシカと皇弟の関係は、千尋とカオナシの関係と同じなのだ。
そしてその空虚な影は、きらめきの中で浄化されなければならない。もともとこのことについて考え始めたのは、あるサイトで「カオナシよりもハクとの恋物語の方を強調すべきだ!」という主張を読んだことが頭の中に残っていたからだ。今までカオナシがどうしてこんなに大きな存在感を持っているのかということをあまり深く考えて来なかったのだけど、確かに一見関係ないように見えるカオナシがどうしてこんなに扱いが大きく、ポスターやコピーでも取り上げられているのか、考えてみれば不思議だ。
この物語全体をハクと千尋のラブストーリーだと考える見方は新鮮でへえと思ったが、でもこの話はそんなにシンプルではない。これは千尋とハクの恋物語ではなく、千尋の成長の話だ。だとすると、ストーリーで大きな役割を占めているカオナシが千尋と無関係であるはずがない。だとすれば、カオナシは千尋の影なのだと考えるしかない。
カオナシは現実の世界で生きている中で無気力になり始めていた千尋が心の中で飼い始めていた闇なのだ。そしてそれを、闇の中の世界のように見えてそうではなかったあの湯屋の世界に置いて、空虚な自分とさよならして、ある意味浄化され、ある意味大人になって帰って来た。大人になる過程で得たのがハクとの恋の思い出や、救い出した両親への思いなのだ。
そう考えてみると、見え方や行動や性格はともかく、千尋は千を経てナウシカになって行ったのだ。いうことになる。そんなふうに『ナウシカ』と『千尋』の重なりを考えてみると、宮崎が書いてきたいくつもの物語、いくつのも膨大なバリエーションとして立ち現れたそれらの物語の彼方に、一つの壮大な、決して語りつくされることのない物語が見えてきて、感動を覚える。宮崎は語りつくされることのない大きく豊かな物語を持っていて、その壮大な物語の中から、時代と子どもたちの状況に合わせて必要な物語を紡ぎだして来ているのだ、と思う。
これはおそらく、ゲーテがやっていたことと同じなんだろう。物を書く人間の中には、そういう書き方をする人間はいると思う。自分の持っている、まだ形を現していない大きな物語の中から、いかにして一つ一つの物語を紡ぎだして行くか。決して最後まで語りつくせる物語ではないにしても、それを語る話を一つでも多く書けたら、と私も願う。
(この記事は、2011年5月13日にFeel in my bones に掲載した記事をもとに修正したものです)
『ジブリの教科書3 となりのトトロ』を読んだ。
文春文庫から、『ジブリの教科書』のシリーズが出ている。風の谷のナウシカ、天空の城ラピュタに続いて昨年の7月には『となりのトトロ』が出た。2014年1月現在、第4集の『火垂るの墓』まで出ている。今日はこの本について書きたい。
『ジブリの教科書3 となりのトトロ』はかなり読み応えがあって、どんどん読んでしまった。自分の集中度でいえば2の『天空の城ラピュタ』の比ではなく、1の『風の谷のナウシカ』さえはるかに超える。
この本は自然描写についての記述がものすごく多いのだけど、どれだけの手を尽くして自然が描写されているのかということを克明に書いていて、そこにものすごく引きこまれる。
それは自分の身体の中に入っている自然と呼応して、そう、これだよ、これなんだ、と言っている感じがものすごく強い。
この『となりのトトロ』における描写がその後のジブリ作品の自然描写の嚆矢になって、その後のジブリの自然描写の巧みさがどんどん神技の域に入って行く。そしてその時できなかったことが、たとえば『耳をすませば』や『もののけ姫』で実現して行くのだなあということを思わされる。トトロはすごい一歩ではあるけれども、やはり「最初の一歩」なのだ。
それは宮崎作品だけでなく、高畑作品でも『おもひでぽろぽろ』や『平成狸合戦ぽんぽこ』の自然描写につながっていく。今日高畑勲のインタビューを書店で読んでいて分かったのだが、人的に言えばこれは男鹿和雄の仕事と言える面が大きいようだ。
トトロはその第一歩をしるした記念碑的な作品なのだ。
そして驚くのは、ナウシカ、ラピュタとSFっぽい作品が続いたあとにいきなりトトロという企画を実現させたこと。しかも『火垂るの墓』と二本立てで。やはり企画に無理があったのか休み中の公開でなかったために興行収入は上がらなかったようだ。しかしキャラクターグッズは爆発的に売れ、今でもスタジオジブリの収入の柱の一つになり、またジブリを象徴するキャラクターとしてあちこちに登場するのは周知のことだ。
この本をきちんと読んでいくと、この場面はどの色とどの色を使って、みたいなすごい具体的な記述もある。きっと後に続くアニメーターやその卵たちにとっても、本当に『ジブリの教科書』なんだなと思ったのだった。
『かぐや姫の物語』は、一言で言えば、どこまでも味わい尽くしたくなる映画だった。(その6・終)
(その5)から続きます。
映画が終わり、クレジットが流れる中、二階堂和美の『いのちの記憶』が流れる。この曲は、まるでこの映画を長い長い歌、長歌であるとすると、その反歌のような曲だ。「あなたに触れた喜びが」で始まる歌詞は、先ず私が思い起こしたのは捨丸とかぐや姫の場面だが、『Switch』の二階堂和美インタビューによれば、その時妊娠中だった彼女は翁と媼が初めてかぐや姫を抱いたときの喜びから発想したのだという。
この映画は全体にそうなのだが、描かれているのが特殊性のない、誰にでも通じる、すごくイメージ喚起力のある、普遍的なものが描かれていることをたびたび思い知らされるのだが、その「触れる喜び」というものが持つ普遍性というものがこれだけ思い知らされる映画も、歌もないように思った。
語り始めると本当に饒舌になってしまうのだが、この映画は本当に埋め込まれたそれぞれのことがそれぞれ底なしに深くて、高畑監督の底なしの世界の広がりが、教養面もそうだし、思考面もそうだし、違和感を恐れない(それは興行的には必ずしもプラスではないだろう)制作態度も、いまの日本でこれだけのことをやってのけられる監督はほかにいないだろうと思わされた。炭焼きで出ている仲代達也がどこかの本で「日本の劇映画は今ジブリ作品に完全に負けている」と自らを含む映画界の奮起を促していたが、これだけのことができる人がいま日本にいるということは、それだけで素晴らしいことなのだとは思った。
ジブリの映画、特に宮崎監督の映画に出てくる登場人物たちはみな「今の自分を超えて行こう」とする人たちなのだが、高畑監督の登場人物はそうではない。今回のかぐや姫も、ある意味そういう前向きな人たちではない。運命を楽しみ、運命に抗い、激しく抗議し、受け入れ、そして本当の運命を知って、この世に生きることを肯定し、それを強い言葉で述べようとしたときに月の世界の衣を着せられて、「清浄な世界」へと還って行く。『Switch』の対談で川上量生はプロデューサーの西村義明にこれは「女性視点の物語だ」と言い、「(僕の)彼女のわがままは受け入れて上げなきゃだめだな」と思ったのだそうだ。私自身はいつの間にかかぐや姫に一人称の思い入れをして見ていたので女性視点とかなんとかいうことは思いつかなかったが、むしろ「こうやって世の中のルールを受け入れて行かなきゃいけないんだよなー、辛いよな、生きるのは」みたいに見ていた。だからむしろ、「自分のわがままは自分が受け入れなければいけないな」ということなんだと思った。
まだまだ言いたいことは進化中で、たぶん書けば書くほど書きたいことは増えるしまた変化していくので、今の段階での感想という形でこのような形にしておこうと思う。
そんなふうに、『かぐや姫の物語』はどこまでも味わい尽くしたくなる映画だった。鍋のあとにご飯を入れておじやにしても、何度でも食べられそうな感じなのだ。
(終わり)
『かぐや姫の物語』は、一言で言えば、「どこまでも味わい尽くしたくなる映画」だった(その5)
(その4)からの続きです。
月への帰還を前に、都を抜け出した姫は田舎の懐かしい道をたどり、そこで思いがけず大人になった捨丸に再会する。姫は捨丸に「あなたと生きることができたら」と言い、その思いを自らも伝えた捨丸と二人で空を飛ぶ場面。ここまでリアルに作られてきた構成が突然『千と千尋の神隠し』の千尋とハクが空を飛ぶ場面になったのには驚いた。見た瞬間にはかなり否定的にとらえたのだけど、これを「ジブリだから」と安易に受け入れても意味がないし、何というかかなり多くのことを緻密に踏まえたうえで作られている映画だから、むしろその意味を考えたほうがいいかもしれない、と思った。
月の世界の住人であることを自覚した姫は、帝の前で姿を消したり表したりすることができる超自然的な能力を手に入れている。だから捨丸とのくだりも、それを考えれば不自然ではないかもしれないともいえるが、すでに多くの求婚を断っているかぐや姫は子どもではないのであり、子どもの淡い思いを描いた『千と千尋』とは違う。これはむしろ、「子供向きの映画では描けないこと」、シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』にはなかった場面がオリビア・ハッセー主演の映画では描かれていた、ということを思い起こすべきなのかもしれない。インド映画で、カップルがいいムードになると踊りの場面になってしまうような。と歯に衣を着せて書いてみたが、それ以上のことはご想像にお任せだ。
ところで、この世のものならぬかぐや姫とこの世のものそのものである捨丸の位置は、この世のものである千尋とこの世のものならぬハクとの位置が入れ替わっている。千と千尋のオリジナル性とかぐや姫の物語の古層性。大人になる前の世界のある種の完成である千と千尋と、大人になってしまう、そしてこの世にいつまでもいられない哀しみを描くかぐや姫。様々な意味でこの場面は千と千尋との対照性を思わずにはいられなかったので、最初はそれを書こうとして、「『かぐや姫の物語』は「『千と千尋』の裏返し」だった」という題にしようと思っていたのだが、書いているうちにそんなキャッチ―なフレーズはどうでもいいような気になってきてしまった。
まったく脱線してしまった、元に戻ろう。
十五夜の、月の使いが迎えに来る場面は見ていていろいろ混乱した。月の光を浴びると姫がスーッと自動人形のようにひきつけられていってしまうのもなんだか変だと思ったし(理屈で考えれば演出意図は分かるのだが)、迎えに来た仏像みたいな月の王が着ている服もなんだかマツコデラックスみたいだと思った。またあのアジアンな感じの音楽も『平成狸合戦ぽんぽこ』みたいだと思ってすごく違和感があったのだが、「アストラル界の音楽のようだ」という人がいて、なるほどそういうふうに聞くのかと思った。
つまり、あの場面は違和感を感じるべきなのだ、と私は思った。
天国とか月の世界とか「清浄な世界」は、この地上の汚いかもしれないが「生命に溢れた世界」とは違うのだ、ということ。こちらの高畑監督と音楽担当の久石譲さんとの対談で、あの場面に対して監督は「(阿弥陀来迎図では)打楽器もいっぱい使っているし、天人たちはきっと、悩みのないリズムで愉快に、能天気な音楽を鳴らしながら降りてくるはずだと。最初の発想はサンバでした。」という指定を考えたのだという。悩みがないってなさすぎだろ、という感じだが、それを聞いた久石さんもさすがに衝撃を受けて、「ああ、この映画どこまでいくんだろう」と思ったそうだが、その結果「ケルティック・ハープやアフリカの太鼓、南米の弦楽器チャランゴなどをシンプルなフレーズでどんどん入れる」ということになったのだそうだ。アジアンどころではなかった。
清浄な月の世界、天界に、人は単純に憧れるけれども、本当はどうなんだろうか。それに憧れるよりも、この世界を力を尽くして生き、それを味わい尽くすことの方が大事なのではないか。それは宮崎駿『風の谷のナウシカ』のマンガ版で示されていたメッセージでもある。宮崎は「清浄な世界」を「抹殺」したが、高畑はそれをただ淡々と描くことでそれをどう判断するかは観客に委ねている。それは二人の監督の個性の違いでもあるけれども、受け取ってもらいたいメッセージは、そういうことなのだろうと思う。
(その6)に続きます。
『かぐや姫の物語』は、一言で言えば、「どこまでも味わい尽くしたくなる映画」だった(その4)
(その3)からの続きです。
かぐや姫は幻想か現実か定かでない中で懐かしい場所を訪ね、そこにはもう誰もおらず、二度と木地師の子どもたち、(なかでも慕っていた捨丸)に会えないということを知る。それからかぐや姫はおとなしく周りのいうように「高貴な姫」であるという枠に自分をおしこめていく。
そのなかで、眉毛を抜かれるときに一筋の涙が落ちるのが印象的だ。自由と生命の輝きよりも翁の願い、洗練に身を委ねることを選択し、受け入れる。大人の階段を一つ上るときに感じる何かを失ってしまう哀しみ。
それを拒むことを社会の側、大人の側、文化の側からは「わがまま」だというのだけど、この悲しみ、痛みを描くことこそがこの映画の一つの眼目であって、それは小さな「死」でもある。一つ一つ大人になっていくということは、一つ一つ死んでいくことでもあるのだ、という見えないテーゼが描かれている。
最後にかぐや姫は、地上の「すべてを忘れて」月に帰って行くわけだけど、それはやはり死の隠喩でもあり、『Switch』インタビューで二階堂和美が言うように、「呆け」の隠喩かもしれない。『かぐや姫の物語』が切ないのは、急ぎ足で大人になって、急ぎ足で去っていく、その生の儚さが、生命に満ち溢れた場面がより華やかであるだけに、より胸に迫るからだろう。
満開の桜の下ではしゃいでくるくる回る圧倒的な場面のあと、ぶつかってきた子供に姫は現実に引き戻される。それは竹取の翁たちと暮らしていた家にいてぼろぼろの姫に施しをした女の子どもだった。その女が姫に平謝りする姿を見て、姫は却って落ち込んでしまう。食べ物を恵まれたときにはいささかの屈辱も感じていないのに、中身は同じ自分がりっぱな着物を着ているだけで平身低頭される事実に心底落ち込んでしまうのだ。自分がもう、「いのち」の側にいないことを、とことんまで思い知らされて。
そして『竹取物語』で一番印象的な、五人の貴公子の求婚とかぐや姫の拒絶、そして貴公子たちの涙ぐましい努力とその失敗の場面。ここがこんなに効果的なかたちで物語構造に組み込まれるというのも予想外だった。
五人が出てくる順序は原典とは異なっているが、最初に宝物を捏造した車持の皇子が出て、エピソードは原典と同じくコミカルに展開するかと思ったら、次に出てくる阿部の右大臣は全財産をつぎ込んだ鼠の皮衣が焼けてしまい、龍に挑んだ大伴の大納言は遭難しかけ、純粋さを装って口説こうとした石作の皇子に心を動かされたかぐや姫はその女たらし振りを北の方に暴露されて却って大きなショックを受け、最後に宝物を手に入れようとした石上の中納言は墜落死したことを知って、自分が縁談を断るために言った口実が皆を不幸にしたことを知りさらに大きなショックを受ける。
姫は箱庭を破壊して「自分は偽物だ」と嗚咽する。自分のありたかった姿と、今ある自分の大きなギャップ。偽物としか言えない自分の姿に苦しむ。あまりにも純粋でありすぎるけれども、これはつまりは「大人であることの苦さ」だろう。自分は自由に生きたいだけなのに、周りを苦しめ、しまいには死に至らしめてしまう。その戸惑いは、多かれ少なかれ多くの人が感じることがあるのではないか。
そして帝の求愛の場面。その思いもかけない登場に思わず姫は月の世界に助けを呼んでしまう。そして、そうした以上は月に帰らなければならないという事実を知る。そして自分がなぜ地上に憧れたのか、という事実も思い出す。
パンフレットの「プロダクションノート」に「大空に憧れた少年を通し、どんな時も力を尽くして生きることの大切さを伝えようとした『風立ちぬ』。一方、大地に憧れた少女を通し、辛いことや大変なことがあってもやってみなければならない、自らの”生”を力いっぱい生きることの大切さを伝えようとする『かぐや姫の物語』。「この世は生きるに値する」。もしかしたら二人は同じことを伝えようとしたのかもしれない。」とある。
大地への憧れ、生の喜びへの憧憬こそがいわば堕天の罪であった、というのは、ある意味「原罪としての生きること」という解釈も可能かもしれない。しかしそれはキリスト教的な強迫的なものではなく、むしろ「この世にし楽しくあらば来む世には虫に鳥にも我はなりなむ」(大伴旅人)という、現世の生を力強く肯定する思想が表現されているというべきだろう。
この物語は、思うように自分の生を生きられないかぐや姫の姿を通して、自分の生を生きることの素晴らしさをより強く訴えかけているのだ。人は誰でも、そのパラドクシカルな事実を生きなければならないということを。
(その5)に続きます。
『かぐや姫の物語』は、一言で言えば、「どこまでも味わい尽くしたくなる映画」だった(その3)
(その2)からの続きです。
まさに「生きたいように、生きている」日々を送っていたかぐや姫は、「誰もが憧れる都の暮らし」をさせてやろうという翁の願いによって都に出ることになる。
かぐや姫と翁と媼は都に出て大きな屋敷に住み、相模という家庭教師をつけ、斎部秋田という学者に「なよ竹のかぐや姫」という名前を付けてもらい(それまではタケノコのようにぐんぐん成長することから、「竹の子」と呼ばれていた)、髪上げの儀式が行われ、お披露目が行われる。ここのあれよあれよという展開の中で、かぐや姫の「自然」が奪われ、「文化・社会」の中に押し込められていく。それに抵抗しつつ、翁の願いを無礙にもできない。かぐや姫は都の屋敷の庭に田舎の風景を再現するなど、バランスを取りながら順応しようとしていくのだが、自分が御簾の中にいたまま開かれるお披露目の宴会の席で侮辱的な言葉を聞き、我慢しきれなくなってしまう。姫は屋敷を抜け出し、山の中に走っていくと、もと住んでいた田舎の家を訪ねるが、そこには見知らぬ人が住んでいて、知っている人はもう誰もいない。そして、ぼろぼろの姿で家の前に立った姫の前に施しが置かれ、住人は中に引っ込んでしまう。
ここがまた一つ印象に残るところだ。彼女は「施し」を拒まない。もらってよかったと思っているのか、その握り飯をほおばりながら道を降りていく。するとそこに炭焼きをする老人がいて、木地師たちは木を求めて場所を変えて行った(この辺、放浪民を描く網野史学が踏まえられていて、その意味で『もののけ姫』にも通じる世界がある)と姫に教える。
歩き疲れた雪の中で姫は倒れれるが、気がつくと元の京都の屋敷の御簾の中にいる。この雪げしきの描写と姫が着た衣装の純白が重なっているところは、絵で見せるアニメーションだからできることだなと思う。それは後に出てくる月の世界の真っ白な(色のない)清らかさと重なっていく。
行き倒れそうになる死に近い雪の世界=喜びも哀しみもない清浄な月の世界=都でかぐや姫が着せられた純白の衣裳。このイメージのメタファーの力が、生気に満ちた子どもの頃の風景や満開の桜の下で踊る姫のイメージに対比されて、もの悲しい。
この雪の中の炭焼きの声が実は仲代達也だ。この「大物がちょっとだけでる」という手法は芝居や映画では、「御馳走」と呼ばれるわけだけど、この映画ではほかに石作の皇子の北の方(まあ平安時代に北の方という呼称はないと思うが)の声を朝丘雪路がやっているというのもある。
朝丘はともかく、仲代もそうだけど、そのほかのキャラクターがみな声優をやった人たちの顔や姿かたちをどことなく思わせる風貌になっているのも、プレスコアリングというこの映画の特性が生かされていて面白いなと思った。
話はさらに脱線するが、私がこの映画で一番好きなキャラは(まあ主役のかぐや姫をのぞけばということだが)「女の童」(かぐや姫に仕える童女)なのだけど、この声をしている方はずいぶんきりっとした女優さんだ。この役はなんというか、いわゆる「おいしい役」で、まあ、私は芝居をしていた時によくこの種の役を演じていたので、なんだか思い入れを持ちやすいのかもしれないという気もする。ある種のトリックスターだから、構造がしっかりすればするほどその枠に収まりきれないで目立つことができて、印象に残る。そういう配役構造が、実は古典的に作られていて、観客に見えない安心感を与えているように思う。
(その4に続きます)
『かぐや姫の物語』は、一言で言えば、「どこまでも味わい尽くしたくなる映画」だった(その2)
(その1)からの続きです。
この映画がどういう映画であったか、というのを説明するのは難しい。つまり、こういう映画だったと説明しにくい映画なのだ、という言う意味で、味わい尽くしたくなる映画だ、というのが最もぴったりくる感じがする。
もちろん、ただ訳が分からない映画だったらそうは思わないわけで、ものすごく魅力的な画面が溢れているのに、その全体が把握しきれないから、一言では言えないということで、だからこそもっとこの映画がなんであったのかを知りたい、という気持ちに駆られるということで、昨日からずっと『Switch』の特集を読んだり、パンフレットを読んだり、ウェブ上の感想を読んだりしていた。
絵は、とにかくすごい。動画も、これが動画だったらほかの映画は何なのかというくらい。『進撃の巨人』アニメもつぎ込まれている巨大な情熱や質量は他に類を見ないものであるのだが、まあ映画とテレビアニメという性格も、若い人たちがつくるアニメと「巨匠」が限界を超えた製作費をつぎ込んで作っている映画という背景も全然違うので全然同列で語れるようなものではないのだが、この異様な何もかもやりきった感というか、画面を追っていてなんだか呆れてくる。
プロデューサー見習の川上量生さんが、ジブリではアニメとはなんだと考えられているか、という問いに答えて「絵が動くこと」と答えている。これはなんというか当たり前のようでいてものすごく深い、というかつまり「絵」の「動かし方」こそがアニメの「表現」なのだということだ。ストーリーももちろん大事にはされているが、もっと大事なのは絵が動くということそのもの。どういう絵を描くのか、どのように動かすのか、それが徹底的に考えられ、試され、その繰り返しの中で生まれてきたものだから、この映画の完成に8年かかった。(『風立ちぬ』と同時公開という縛りがなかったらもっと遅れたという。同時公開には結局間に合わなかったが)
だから私も、とにかくどういう絵が描かれているか、そしてそれがどのように動かされているのか、というところにテーマを置いてみていた。そして、その達成度の大きさに、目を見張らざるを得なかった。
最初はあのラフなタッチ(あれは筆で書かれていると思ったが、実は鉛筆の線なのだそうだ。小さな画用紙に書かれた鉛筆の線を映画の画面にまで拡大すると、筆で書かれたように見えるらしい(『Switch』のインタビューでかぐや姫の声をやった朝倉あきが高畑監督に聞いた話として話していた)が存分に動いていて、あのひょっという感じの少女が悪童たちにはやされて着物を脱いで裸で川に飛び込んだりする場面が、小島功の黄桜の河童のコマーシャル(動画が出ます)を思い出させたが、いま黄桜の動画を見直すとやはりなんだか通じるところがある。もちろん動画の精度は全然違うけど。
あの、木地師の子どもたちと遊んだり走り回ったり川に飛び込んだり畑の売りを盗んで食べたりする描写は、見終ったいま思えば作品のテーマである「いのちの輝き」を最もあらわしている場面だ。
ものすごく今思うとじんとするのだけど、なんというか、この映画はものすごく言いたいことが理路整然と疑問の余地なく配置されている映画で、そういう意味でなんかそこまで理詰めで作っていいんかな、という感じが見終った後もすごく残った。ただ逆に、ものすごく理詰めであるから不必要な場面が一切ない、というものすごく緊密な構成になっている。わからないという印象があるのは理詰めでないからではなく、たぶんあまりに理詰めすぎるということもあるのだろうけど、わざと省略されている、書かれていない部分があるからで、関連資料をあたっていると、そうかそこはそういう設定だったのかというのが割とすぐわかって、空白が寸分の隙もなく埋められていき、息苦しいくらいになる。
この場面について、裸の女の子が水に飛び込んだり、授乳の場面で乳房が描かれていることを、国際基準に照らして問題だと言っているブログがあって、バカじゃないのと思ったが、まあこれは宮崎駿が『風立ちぬ』で何の遠慮もなくたくさんの登場人物がたばこをプカプカふかしているのと同じで、言うべきこと、描写すべきことがあるときにそういう中途半端な政治的配慮はしない、という潔さがいいのだと思うし、また今書いたようにあの場面は生命力が溢れている、いのちが輝いているということの描写のために、日本の昔の子どもたちや母たちの最も自然な状態がそのまま書かれているだけで、逆にそういう価値観を伝えるべきだとすら思う。
まあこのことは言い出せばきりがないんであって、一度取り締まる決まりが、非難する口実ができるとこの程度の描写も児童ポルノまがいに言い立てるのはどうかと思う。
日本では、子どもが裸で走り回ったり、お母さんが電車の中で授乳したりするのは昭和40年代でさえ珍しくなかった。それを持って野蛮の象徴のようにしたり顔をする人種差別感情もどうかと思うし、それに迎合しようとする植民地的文化人もどうかと思う。一つ目小僧の国で二つ目が差別されても、二つ目が二つ目の文化を譲る必要はないだろう。
……なんだかムキになったが、とはいえ日本でも都会から順番にそういうものを隠す方向へ動いていることは事実ではあるので、ある意味無駄な抵抗かもしれないが、まあだからこそそういう子どもがはしゃいでる裸な姿にいのちの輝きを見せようとする意図が意味あるものに見えるのかもしれない。
(その3)へ続きます。
![千と千尋の神隠し (通常版) [DVD] 千と千尋の神隠し (通常版) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QNjf%2BqXWL.jpg)